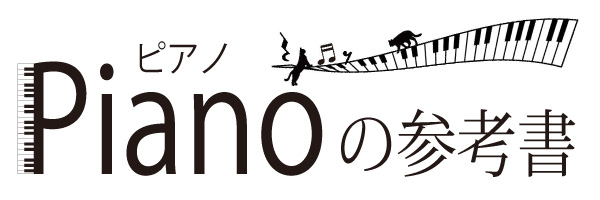森と、ピアノと、──「ピアノの参考書」視点で読み解く“本来の自分”と音楽の居場所

はじめに
2025年春、長野県茅野市と富士見町の森の中に、ひときわユニークな場所が誕生しました。その名も 森と、ピアノと、。 ここは“とっておきのおひとりさま時間”をテーマに、誰にも邪魔されず、ピアノやアートなど自分の「好き」に没頭できる完全プライベート空間です。
ピアノの教室や教材、学び方を紹介してきた当サイト だからこそ見える、この場所の価値と意義。ピアノ学習の本質や、音楽と人間の関係性を深堀りしながら、「森と、ピアノと、」の魅力を考察します。
1. 「森と、ピアノと、」が生まれた背景
現代社会は、SNSやデジタルデバイスに囲まれ、誰もが常に「誰かの目」を意識し、評価や比較の波にさらされています。ピアノ学習も例外ではなく、動画投稿やSNSでの演奏披露が当たり前になり、他者の評価がモチベーションや自己肯定感に直結する時代です。
そんな中、「森と、ピアノと、」は“本来の自分”と向き合うための場所として誕生しました。代表の廣瀬明香さん自身が、薬剤師としての多忙な日々や家族の病気を通じ、「生きる」とは何か、自分らしさとは何かを問い直し、森の静寂の中でピアノを弾く時間に心からの安らぎを感じたことが、このプロジェクトの原点です。
2. 施設の特徴──「音の間」と「色の間」
「森と、ピアノと、」は、1日1組限定の完全プライベート空間です。施設は「音の間」と「色の間」という2つの部屋で構成され、どちらも大きなガラス窓から森の景色が広がります。
音の間:森の音と一体になりながら、ピアノや他の楽器を自由に奏でることができます。設置されているのは、1965年製のオールドヤマハのグランドピアノ。合成樹脂やプラスチックを使わず、膠や鹿の皮など自然素材と職人の手仕事で作られた、現代では希少な一台です。
色の間:森で拾った葉や枝を使って紙に写し取ったり、イーゼルを持ち出して森の中で絵を描いたりと、自由なアート体験ができます。
チェックイン時にはスマートフォンなどのデジタルデバイスを預け、完全なデジタルデトックス環境で五感を研ぎ澄ませることができます。
3. ピアノ学習と「没頭」の価値
「ピアノの参考書」では、ピアノ学習の上達において“集中”や“没頭”がいかに重要かを繰り返し伝えてきました。ピアノのテクニックや読譜力、表現力は、日々の積み重ねと、時に自分だけの世界に没入する時間から生まれます。
教材選びの本質:初心者にはメソードブックやハノン、中級者にはエチュードやクラシック曲、上級者には即興や創作教材と、段階に応じた教材選びが重要ですが、どのレベルでも「自分の好き」に没頭できる環境が上達のカギです。
評価からの解放:SNSや発表会、コンクールなど「他者の評価」を意識する場も大切ですが、時には“誰にも聞かれない”環境で、ただ自分のためだけにピアノを弾く時間が、音楽との本質的な向き合い方を取り戻してくれます。
「森と、ピアノと、」はまさに、ピアノ学習者が“評価”や“役割”から解放され、自己表現に没頭できる理想的な空間です。
4. 五感を解き放つ──森とピアノの相乗効果
ピアノの上達には、「音」だけでなく「身体感覚」や「空間認識」も不可欠です。森の静寂、鳥のさえずり、木漏れ日、澄んだ空気といった自然の刺激は、普段の練習室では得られないインスピレーションと集中力をもたらします。
音の響き:グランドピアノの音色が森の静寂に溶け込む体験は、楽譜の指示やテクニックを超えた「音楽そのもの」との対話を生みます。
身体感覚:自然の中で深呼吸し、リラックスした状態で鍵盤に向かうことで、余計な力みが抜け、より自由な演奏が可能になります。
創造性の解放:森の中での即興演奏や、自然素材を使ったアート体験は、日常の枠を超えた創造性を引き出します。
5. 「ピアノの参考書」的視点で見る“学び”の本質
ピアノ学習の現場では、しばしば「正しい弾き方」「効率的な練習法」「上達のための教材選び」といった“合理性”が重視されがちです。しかし、音楽の本質は「自分の感性」と「好き」という気持ちに根ざしています。
個別最適化の極致:「森と、ピアノと、」は、1日1組限定という徹底した個別最適化の場。ピアノ教室でも個別指導の重要性が語られますが、ここでは“指導”すらなく、完全に自分のペースで音楽と向き合えます。
教材を超えた学び:どんな名教材も、自分の「好き」に没頭する時間には敵いません。森の中で好きな曲を自由に弾く、即興で音を紡ぐ、心のままに音楽を楽しむ──それこそが、ピアノ学習の最も贅沢な時間です。
6. デジタルデトックスと“今ここ”にある音楽
現代のピアノ学習は、アプリやオンライン教材の普及で便利になった一方、常に「情報」と「比較」にさらされています。ピアノ練習アプリも有用ですが、音の強弱や音色、手のフォームや姿勢といった細部は、実際の楽器と空間でしか体得できません。
「森と、ピアノと、」ではデジタルデバイスを預け、森とピアノだけの“今ここ”に没頭します。情報の波から一旦離れ、五感と感性を研ぎ澄ますことで、普段は気づけない自分自身の音楽的な可能性が目覚めるのです。
7. 地域資源とピアノ──新しい「音楽の居場所」
森と、ピアノと、は単なるレンタルスペースではありません。長野県茅野市・富士見町の豊かな自然資源を活かし、地方創生や新しいデスティネーションとしての可能性も秘めています。
地域と音楽の融合:都会のピアノ教室やホールでは得られない、森と音楽の融合体験。地元の人も、遠方から訪れる人も、ここでしか味わえない「音楽の居場所」を手に入れることができます。
アートイベントやワークショップ:今後はアートイベントやワークショップも企画される予定で、ピアノを中心に多様な表現活動が広がっていくでしょう。
8. 「森と、ピアノと、」が問いかけるもの
「森と、ピアノと、」は、 あなたが「誰か」になる必要のない場所。役割も、肩書きも、期待も──すべて森の入り口にそっと置いて、ただ「わたし」としていられる、自然と溶け合う時間です。
ピアノを学ぶ人、教える人、楽しむ人すべてにとって、音楽は「評価」や「成果」だけでなく、「自分のまんなか」と出会うためのもの。森と、ピアノと、は、そんな音楽の原点を静かに思い出させてくれる、現代における“音楽のサンクチュアリ”です。
9. まとめ──「好き」と向き合う贅沢
ピアノの上達には、正しい練習法や教材も大切ですが、何より「自分の好き」と向き合う時間が不可欠です。「森と、ピアノと、」は、日常の役割や評価から解放され、森とピアノに抱かれながら、ただ「好き」に没頭できる場所。
ピアノの参考書として伝えたいのは、教材や教室選びの先にある“本当の学び”──それは、森の静寂の中で自分の音と向き合う、そんな贅沢な時間なのかもしれません。
「森と、ピアノと、」で過ごす一日が、あなたのピアノ人生に新たな色と響きをもたらしてくれることを願っています。