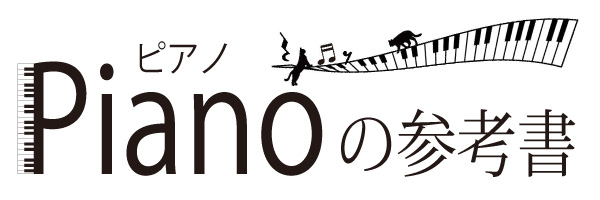ショパン国際ピアノコンクール第2回(1932年)入賞者紹介

1932年、第2回ショパン国際ピアノコンクールは、前回を大きく上回る規模で開催された。世界中から200人を超える応募があり、実際には14カ国68名がワルシャワの舞台に集った。コンクールの権威と注目度は一気に高まり、審査員もヨーロッパ各国から錚々たる音楽家が集結。ピアニストのマルグリット・ロン、マグダ・タリアフェロ、カルロ・ゼッキ、作曲家モーリス・ラヴェルやカロル・シマノフスキが名を連ねるなど、国際色に富んだコンクールとなった。
第2回入賞者の顔ぶれとエピソード
この大会最大のドラマは、“コイントス”による第1位決定である。トップに並んだのは、ロシアを亡命後フランスで活動していたアレクサンドル・ウニンスキーと、ハンガリー出身で全盲の天才ピアニスト、イムレ・ウンガル。甲乙つけがたく同点となり、厳正な国際審査員団も議論の末に「コイントス」で勝者を決定するという前代未聞の結末となった。運命のコインはウニンスキーに微笑んだ。芸術の最高峰が偶然の力で決まる――歴史に残るエピソードである。
第2回入賞者は次の通り。
1位:アレキサンドル・ウニンスキー(ロシア→フランス)
2位:イムレ・ウンガル(ハンガリー)
3位:ボレスラフ・コン(ポーランド)
4位:アブラム・ルーフェル(ソ連)
5位:ラヨス・ケントネル(ハンガリー)
6位:レオニード・サガロフ(ソ連)
7位:レオン・ボルンスキ(ポーランド)
8位:テオドール・グートマン(ソ連)
マズルカ賞はウニンスキーが受賞。彼のショパン解釈は洗練されながら詩情に満ち、後にアメリカに渡って多くの弟子を育てる名教師となる。ウンガルは障害を乗り越えて熱烈なファンを獲得し、ヨーロッパ各地で活躍。コンクール初期にして、「国際性」と「多様な演奏スタイルの素晴らしさ」を世界に示した大会だった。
第2回大会の特徴と時代背景
第1回大会を成功させたポーランドは、コンクールを「世界に向けた文化発信の場」と位置付けた。当時のヨーロッパは、芸術の競争化への賛否がうずまく一方、ショパン音楽継承への情熱は広まり、若き演奏家たちの夢とロマンがワルシャワに集まった。審査員のグローバル化により、“国籍や障害を越えた純粋な演奏芸術”が評価される大会へと進化。全盲のウンガルや亡命ピアニストのウニンスキー――多様な生き方を選ぶ人々がステージに立ち、ショパンの音楽が普遍性と多様性を獲得したことを象徴する大会となる。
演奏課題と審査のエピソード
本選はマズルカ、ノクターン、エチュード、ポロネーズ、ソナタ、協奏曲と多彩なショパン作品が課題曲。ウニンスキーはマズルカ賞も受賞し、詩情と技術力が高く評価された。ウンガルの演奏は、聴衆の一人が感動のあまり失神したほど劇的だったとの記録が残る。コンクールは「単なる技術競争」から「芸術の本質を競う場」へと進化した。
入賞者たちのその後
ウニンスキーはその後アメリカに渡り、多くのピアニストを育てた名教師となった。録音も多数残され、ショパン解釈の指標となる名演として今も評価される。ウンガルは全盲のハンディを乗り越え、世界各地で熱烈な支持を獲得。コンクールは音楽だけでなく、障害を持つ人々への社会的理解や、演奏芸術の幅広い可能性を提示した大会でもあった。
第2回大会が残したもの
第2回大会最大の特徴は「芸術作品の順位付け」という本質的な困難への挑戦。偶然による決定法は限界を示すと同時に、多様性・挑戦・芸術への誠実さという価値観を鮮明に打ち出した。若き才能が世界へ羽ばたき、多様性と公正さ、そして芸術的深みを追求するショパンコンクールの伝統が一層強くなった回でもある。
まとめ
第2回ショパンコンクールは、偶然とドラマ、挑戦と感動が詰まった歴史的大会であった。入賞者たちの歩みは、音楽教育者やピアノ学習者にも「技術だけでなく生き方」そのものが重要であることを教えてくれる、価値あるストーリーなのだ。